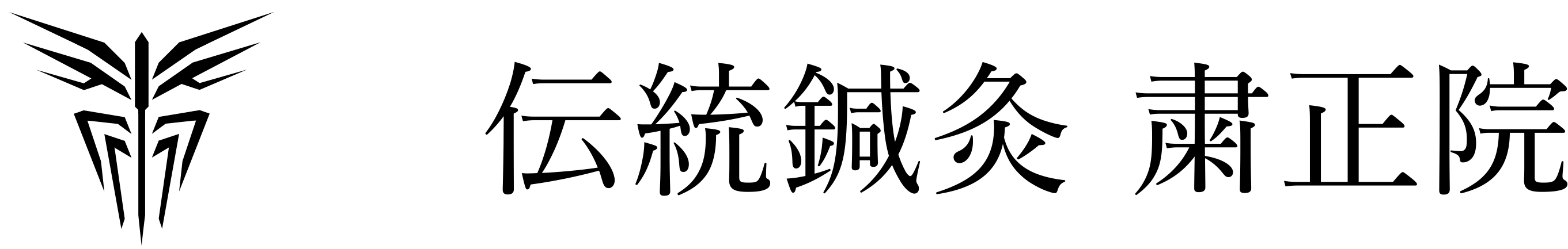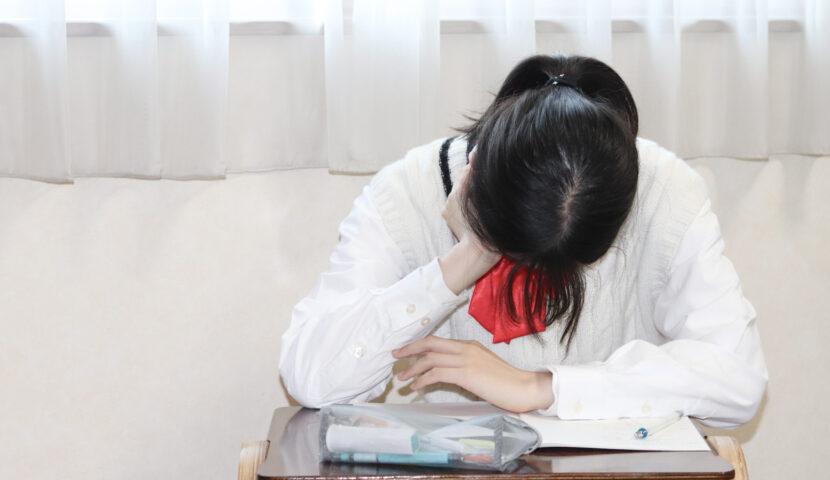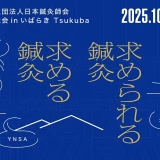起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)の治療経過です。
起立性調節障害は、自律神経の乱れによって、立ち上がったときに脳や全身への血流が低下する病気です。主に思春期の子どもに多く見られます。
患者:10代女性
症状:朝起きられない、倦怠感、立ちくらみ、ふらつき、集中力低下、食欲不振
中学1年生の秋頃から立ちくらみ、ふらつきが出現。
中学1年生の春頃に初潮を迎えていたため、近所の内科では貧血の症状であると診断され鉄剤を処方される。
鉄剤を内服するが症状は改善せず、月経周期に関係なく症状が徐々に悪化していた。
中学2年生の春頃には、朝起きられない、倦怠感で動けない状態の日が増え、学校に行きたいが動けず半月以上休む日が増えてきていた。
もともと瘦せ型で少食だが、食欲と体重が減少し、集中力の低下も出現するようになる。
再度別の内科を受診したところ、起立性調節障害と診断され、非薬物療法として可能な範囲で飲食の摂取と散歩などの軽い運動を指導される。
非薬物療法にプラスして鍼灸治療を知人から勧められ当院へ来院。
増悪因子:朝起床時、午前中
緩解因子:午後になると徐々に動けるようになってくる
主訴発症前(小学校の頃)までは外でよく遊んでいたので、「元気になってまた外でたくさん遊びたい」と問診時に患者からの発言。
五臓六腑の「肝」と「脾」に異常があると診立て、肝・脾に関わる経穴に適宜治療を開始。
治療開始1か月後:午前中のうちに動ける日が増えてきた。食欲も出てきた。症状は全体的に半減。
治療開始2か月後:食欲と体重が戻り、集中力低下もなくなる。学校に行ける日が月の3分の2以上になる。
治療開始3か月後:倦怠感ほぼ消失、朝起床後にすぐ動けるようになる。学校を休む日が月に1~2回に減少。
治療開始4か月後:季節の変わり目や気圧の変化で倦怠感を感じることがあるが、学校には休まず登校できている。
「脾」は、気血の生成や水分の巡りに関係しています。
「脾」が不調になると、消化不良や食欲不振、疲労感、むくみ、下痢、腹痛などの症状が現れやすくなります。
「肝」は、気血の巡りを整えたり、自律神経を調節したり、感情の調整などを担っています。
「肝」が不調になると、気血のバランスが乱れ、体調や情緒に影響を及ぼします。
肝と脾を病むと「肝脾同病」といいます。脾の運化機能に異常が起こると、脾で生成した気血をスムーズに肝に送ることができなくなり、肝の機能も失調させてしまいます。
気虚(気の不足)では、慢性的な疲労感、食欲不振、めまいや立ちくらみなどが起こります。
血虚(血の不足)では、慢性的な疲労感、動悸や息切れ、頻脈、顔色の蒼白化、肌の乾燥や荒れ、不安感や不眠症などが起こります。
今回の患者さんは、肝脾同病 + 気血両虚(気と血の両方が不足している状態)でした。
肝脾に関わる経穴で気血を補う治療を継続したことで、症状が改善した症例でした。
起立性調節障害を放置すると、めまいや立ちくらみ、頭痛などの症状が悪化することが考えられます。
また、 朝起き上がることができなくなり、1日中ベッド上で過ごすことになったりと、社会生活に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
起立性調節障害と診断されても、しっかり治療をすれば完治できる病気です。 周囲の大人が、病気を理解し、怒らず、焦らずに見守りながら子供をサポートしていきましょう。