「意識を失うほど酷い生理痛」の症例(治療経過)です。
はじめに、月経困難症について簡単に説明します。
月経困難症とは、月経に伴う症状により日常生活に支障をきたしたり、寝込んだり、鎮痛剤を必要としたりするものを指します。
月経困難症は大きく分けて2つに分類されます。
・器質性月経困難症
痛みの原因となる器質性病変が骨盤腔内に存在するものです。子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症、あるいは骨盤内炎症などが原因です。
・機能性月経困難症
明らかな病変が見られず、月経の血液を排出するために子宮を収縮させる物質であるプロスタグランジンの過剰分泌により子宮が収縮しすぎる場合や、頸管(子宮の出口)が狭いことが痛みの主な原因です。
この患者さんは、機能性月経困難症による生理痛です。
患者:20代女性
主訴:生理痛(痛み止めを服薬しないと意識を失うほどの激痛)
痛みは鈍痛で冷えを伴い、下腹部に固定性で間欠性の痛み。
服薬しないと手足の冷え、発汗、腰痛、頭痛が出現し、下腹部の激痛で失神する。
増悪因子:冷え
緩解因子:温める、入浴、服薬
月経に伴う症状:不眠、下痢、倦怠感、気分の落ち込み、イライラ
〈既往歴〉
幼少期:水疱瘡。
11~12歳頃:初潮。当時、生理痛はなかった。
中学生:主訴出現。毎月生理痛が酷く、痛み止めを服薬していなかったため日常生活に支障がある。
15歳:蕁麻疹。
高校生:金属アレルギー発症。腕時計の金属部が皮膚に当たると発赤・痒みが出現するようになる。
主訴は変わらず、市販薬のエルペイン(生理痛専用薬)を服薬し始めて生理痛を抑えていた。
専門学生:インフルエンザ。
20代:COVID-19。
〈その他症状〉
豪雨が降る前に頭痛が出現。
寒がりである。
寝つき、寝起きが悪い。
〈治療経過〉
治療開始1か月後:生理痛は普段と変わらない。
治療開始3か月後:生理痛は少し改善。意識は飛ばないが、下腹部痛と腰痛が強い。
治療開始4か月後:仕事中に来潮。痛み止めを飲み忘れたが、服薬しなくても仕事が出来る程度まで痛みは減少している。今回の症状は下腹部痛と腰痛のみ。
治療開始6か月後:生理痛なく、体の怠さのみ。
この患者さんは体質的に肝の気が高ぶりやすく、学生時代から続いているストレスが主訴発症に大きく関与していました。
証(東洋医学的な体質)は「心肝気鬱(心と肝の経絡の気が停滞している状態)」でした。
五臓六腑の「心」・「肝」の異常がメインであると捉え、「心」・「肝」に関わる経穴に治療を行いました。
「肝気の高ぶり」とは、東洋医学において、精神的ストレスや、肝臓の気の流れが乱れることで、イライラ、怒りっぽさ、不眠などの症状が起こる状態を指します。
〈肝気が高ぶる原因〉
精神的ストレス:肝の気の流れを悪くし、高ぶらせる要因となります。
季節の変化:春は肝の気が高ぶりやすい季節とされ、陽気の影響で肝気が乱れやすくなります。
食生活:刺激的な食べ物や、暴飲暴食は、肝の気の流れを悪くします。
運動不足:体内の気の巡りを悪くし、肝の気を高ぶらせる要因となります。
〈肝気の高ぶりと関連する症状〉
精神的な症状:イライラ、怒りっぽさ、不眠、情緒不安定、集中力の低下など
身体的な症状:頭痛、目の充血、めまい、肩や首の凝り、倦怠感など
女性特有の症状:月経不順、生理痛、乳房の張りなど
月経困難症は日常生活に支障をきたすほどの症状が出現することもありますが、運動や食事などの養生に気を付けながら治療を継続することで改善していきます。

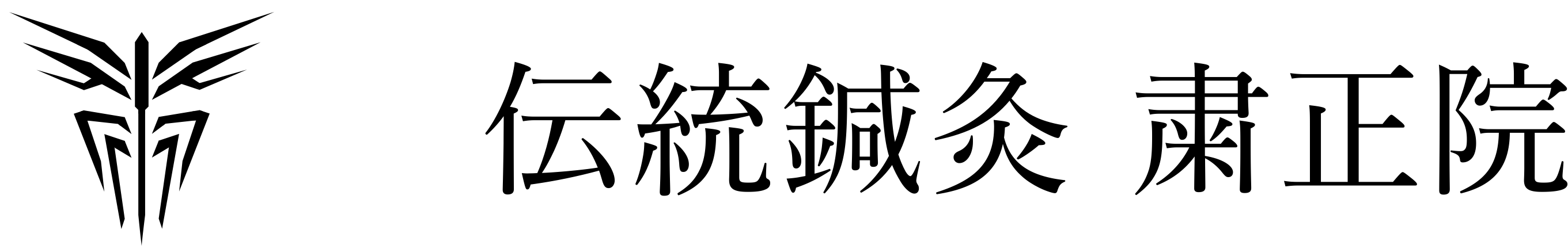










コメント